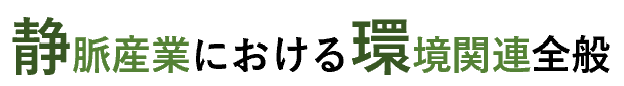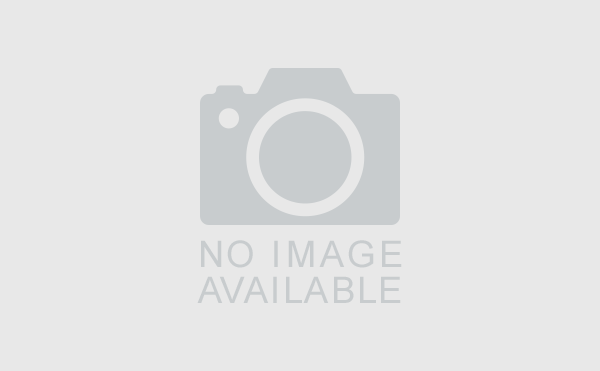【2025年最新】産業廃棄物業界の今後と動向!データを踏まえて解説
2025年を迎え、産業廃棄物業界は「人手不足」という長年の構造的課題に直面しています。少子高齢化の影響下で、新規採用は伸び悩み、熟練作業者の高齢化により技能継承も滞りがちです。その結果、収集・運搬・処理といった現場では作業遅延や安全性の低下といったリスクが顕在化しています。
そんな中で、今後廃棄物業界はどういった方向に進むのか、どのように人手不足の問題に向き合っていくのかを、中小企業診断士の立場も交えて解説していきます。
持続可能な産廃ビジネスへと舵を切る経営者や現場担当者に向けて、新たな商機と解決策のヒントにしてください。
1.産業廃棄物業界の現状
①産業廃棄物排出量の変化
②業種別排出量の内訳
③種類別排出量の内訳
④産業廃棄物の処理状況
①産業廃棄物排出量の変化
全国の産業廃棄物の排出量はH8年度をピークに、リサイクルの意識の高まりと共に、ゆるやかに減少し、近年では令和5年度に3億6,500万トンとなり、令和4年度実績から約900万トン減少しています。
②業種別排出量の内訳
産業廃棄物の業種別排出量について、「電気・ガス・熱供給・水道業」が最も多く、次いで「農業、林業」そして建設業となっている。事業の規模に応じた順位であり、この3業種は他の業種とは頭一つ抜けている。パルプ・紙・紙加工品製造業、鉄鋼業を含めた合計5業種では全排出量の約8割を占めています。
③種類別排出量の内訳
産業廃棄物の排出量を種類別に見ると、汚泥の排出量が最も多く、次いで動物のふん尿、がれき類となっており、この3品目で全排出量の約8割を占めています。汚泥については排水処理工程で発生するケースが多いが大半は脱水処理されるため、実際の廃棄物量とは乖離があります。
④産業廃棄物の処理状況
全体の構成として、最も人手を解さない埋立比率は2.4%しかなく、ある程度工数が必要となる再生利用や減量化が大半を占めています。
2.産業廃棄物業界が直面する課題
産業廃棄物の物量は年々減少してきていますが、産業廃棄物が無くなることはありません。
処理方法については、以前のように焼却して埋立という方法は、最終処分場を新たに設置することが難しいことや、再資源化・リサイクルの考え方が一般化した昨今においてはベストな方法ではありません。
再資源化・リサイクルを実施する場合、原料となる産業廃棄物には分別の徹底が必須となります。様々な場所から依頼を受けると分別を徹底されているお客様からそうでないお客様まで様々おられます。こういったお客様の廃棄物に対応するためには多くの人員が必要となります。
また、施設の処理能力にも気を配らなければなりません。一度に搬入できる量には限界があります。よって大量輸送でガンガン運ぶといった運用ではなく搬入量に制限がかかるケースもございます。
このように、処理の方法がより多様化することで、より多くの人員が必要となってきています。
しかし、産業廃棄物の業界は昔から「3K」(きつい、汚い、危険)の代表格と認識され人手不足の解消が大きな課題となっています。
3.人手不足解消に向けた取組み
人手不足を解消するための取組みとして以下の3つ上げます。
①社内DX化への取組み
②外国人材の受入れ体制作り
③同業者同士の連携
①社内DX化への取組み
人員不足を解消するためには今まで人で対応していた業務をIT技術を駆使してデジタル化、自動化していくことで人がしていた業務を移行させていくことが望ましい。
取っ掛かりとして、まずは、紙をデータ化することから始めてはいかがだろうか。AI機能を搭載したOCRはそのような要望に限りなく理想に近い状態で答えてくれます。
②外国人材の受入れ体制作り
2027年より政府は、外国人労働者の受け入れを拡大するため、在留資格「特定技能」の対象分野として新たに倉庫管理、廃棄物処理、リネン供給の3分野を追加する方針を固めました。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250515/k10014806961000.html
これにより、今までできなかった外国人の雇い入れが可能となり、新たな選択肢が増えることになります。
③同業者同士の連携
営業や収集運搬については、同業者同士で連携することで人手不足の問題が解消される可能性があります。産業廃棄物は20種類ありますが、すべての処理を対応できる業者はそう多くありません。
そこで、バッティングしない領域同士の同業者であれば一人の営業担当者が複数の処理先への提案を実施できないでしょうか。
また、収集運搬時の帰り便が空のケースを解消するために、同業者同士の情報連携が図れれば、そういったムダを減らすことができないでしょうか。
4.今後の展望と業界の持続可能性への道
産業廃棄物の発生量が今後増加する可能性は低いですが、環境問題に対する世間の関心は毎年上がっており、政府の方針にもあることから脱炭素や再生可能エネルギーへの関心度はますます高まっていくことが予想されます。
日々、技術が進歩しており新たな技術は新たなビジネスチャンスでもあります。
チャンスは突然目の前に現れます。そのチャンスを掴むためには今の内から人手不足解消に向けた取組を開始する必要があります。
5.まとめ
産業廃棄物業界は、脱炭素や循環型社会の実現に向けて、今後ますます社会的な役割が高まっていく一方で、人手不足という深刻な課題に直面しています。しかし、この課題は逆に、業界の変革と成長のチャンスでもあります。
まずは、①社内のDX化による業務効率化を進めることで、限られた人員でも高い生産性を実現することが可能です。また、②2027年からの外国人労働者の受け入れ拡大は、人手不足の大きな打開策となります。加えて、③同業者間の連携や協業も、人材不足の解消とサービス向上の両立に繋がる有効な手段です。
環境規制の強化や再資源化ニーズの高まりなど、業界を取り巻く外部環境は急速に変化しています。こうした変化を的確に捉え、補助金や各種支援制度を活用しながら、持続可能で競争力のある企業づくりが今こそ求められています。
未来の産廃業界は、単なる「廃棄物処理」ではなく、「資源循環」と「環境価値の創出」へと進化しています。その潮流に乗るためにも、人手不足への対応を経営戦略の中心に据え、今から積極的に動き出すことが重要です。